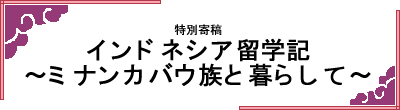
|
第3回
|
|
中央大学 総合政策学部 国際政策文化学科 谷口 愛
|
|
【Fami Mail】 特別寄稿連載
|
|
|
|
|
|
バリ島での爆発テロ事件の第一報を聞いたのは、朝のラジオ放送でだった。とっさに様々なことが頭をよぎった。大学生活のうちの1年間を過ごしたインドネシア。けだるい空気がゆっくりと流れていく赤道直下の生活では、差し迫った危険を感じることは全くなかった。9・11以降、世界中で何かが変ってしまった。いや、そのずっと以前から少しずつ、歯車は狂いだしていたのだろう。かんかん照りの太陽の下、インド洋を望んで過ごしたあのときは、平和そのもののように思っていた。これから私が寄せるものはただの個人的な留学記に過ぎないが、バリ島の一件でインドネシアという国が少しだけスポットライトを浴びたことをきっかけに、一人の日本人大学生が見たインドネシアの別の側面を紹介できたらと思う。 (この留学記は、中央大学父母連絡会が発行している「草のみどり」151号〜154号に掲載されたものから抜粋したものです。) |
|
|
|
||||||
|
第一回目の寄稿にも書いたが、私は当初、インド洋に浮かぶメンタワイ諸島の中のシベルート島研究をしたくて、インドネシアへ留学することにした。しかし、留学先大学でシベルート島研究を行っている教授が、私と入れ違いでジャカルタの大学へ1年行ってしまったことやその他の理由で、研究テーマを代えることとなった。留学する以前から文献を読んで大変興味のあった「母系社会のミナンカバウ族」を追うことにした。実際にミナンカバウ族と生活をともにすることで、日常生活から彼ら独特の世界へのアプローチを試みた。 |
|
|
|
<結婚式の様子。写真は姉妹合同の結婚式の模様>
|
|
| 母系制であるミナンカバウ族社会では、子どもと財産は母親のものである。財産とはお金だけでなく、ミナンカバウ族にとって重要な土地や家畜、家や木なども含まれる。母親がもつ財産は、母親の死後、女の子どものみで分けられる。今では状況が変わってきているが、男性には、基本的に財産の所有権がないというのがミナンカバウ族の伝統である。 ミナンカバウ族は「スク」と呼ばれる氏族のようなものに必ず属している。母親と子どもは同じ氏族に属すが、父親である夫は、彼の母親の氏族に属し結婚したからといって妻の氏族に変わることはない。ミナンカバウ族の結婚では、男性が女性の家に嫁ぐ。ある地域では、結婚する際に女性は、相手の男性に見合った額のお金を男性側に支払うという習慣もある。今では結婚した男女が両親と離れて自分たちの新しい家に住むことは普通になったが、それでも、男性が女性の実家に住むことはよくある。昔は、夫が夜の間だけ妻のもとへ行く「通い婚」であったという。母系社会であるミナンカバウ族の社会では、男性は肩身の狭い思いをしているような印象を受ける。実際、ミナンカバウ族の間で男性は「切り株の上の灰」(=風が吹くとあっという間に飛ばされてしまう存在)と言われている。しかし、男性にまったく権限がないわけではない。男性はそれぞれの家族や親族内で何かを決める際の決定権をもっている。親族の中のまとめ役で長的な存在であるプンフルーは男性が担う。ミナンカバウ社会では、女性が経済を、男性が政治をそれぞれ担っているのである。 |
|
|
|
|
<ルマ・ガダン>
|
|
|
ルマ・ガダンとは、ミナンカバウ族の伝統家屋のことであり、直訳すると「大きな家」という意味を持つ。ミナンカバウ族のルマ・ガダンは非常に特徴的な形をしており、反り返ったような屋根は、水牛をかたどっている。これは、12、3世紀ごろミナンカバウの土地が、ヒンズー教のモジョパイト王国軍に攻撃されたことがあり、その戦いがいつまでも終わらず、両軍共に疲れ果てたすえに、水牛同士をたたかわせて勝敗を決めようということになった。モジョパイト軍は頑強な水牛に十分な餌を与えて戦いにのぞんだ。これに対してミナンカバウ族の西スマトラ軍は子どもの水牛に前日から餌も与えずに戦いに向かわせたのである。いざ、決戦となるや、大牛の乳をもとめて空腹の小牛は相手の腹の下に飛び込んでいった。小牛の角には短剣が結ばれており、一瞬にして勝敗は決まった、という伝説が人々の間で語り継がれている。それ故、ルマ・ガダンの屋根も彼らの象徴である水牛をかたどったものになったという。ちなみに、それ戦いがきっかけとなって、ミナン=メナン(勝利)カバウ(水牛)という名前になったと言われている。(佐藤 多紀三「インドネシア民族文化」雄山閣出版 1986年参照) ルマ・ガダンは高床式で、正面から見て横に長く伸び、家の奥行きは二つの部分に分けられ、後方半分は壁でいくつにも仕切られて寝室に使われる。ルマ・ガダンに住む結婚した女性には、一部屋が与えられ、昔はその部屋に夫が通ってきた。寝室は女性のための特別な部屋で私的なものである。家の正面部分は仕切りのない広間で、ルマ・ガダンに住む家族がそれぞれに食事をとったり、お客を接待したりする。ルマ・ガダンはミナンカバウ族のシンボルであり、結婚式やその他の行事が行われたり、親族のミーティングの場でもある。 西スマトラ州の州都であるパダンでは、郵便局や銀行など、町にあるありとあらゆる建物にこの水牛型の屋根が使われているが、実際に伝統家屋としてのルマ・ガダンに暮らす人は少ない。しかし、西スマトラ州の田舎では今でも、古いものから比較的新しいものまで数多くのルマ・ガダンを見ることができる。そこでは、伝統的な暮らし方ではないにしろ、今でも、人々の日常生活が営まれている。ルマ・ガダンを建てるのには費用がとても高く、現在では新築する人はめったにいない。故に、近い将来、このルマ・ガダンは消滅するのではないかと言う人もいるが、ミナンカバウ族の母なる土地に建つ、彼らの象徴とも言えるルマ・ガダンはそう簡単には消滅することはないのではないかと思う。 |
|
|
|
|
<Solokの田んぼ>
|
|
|
私が1年間暮らした町、パダンの「パダン料理」はインドネシアを代表する料理の一つである。パダン料理店は大都市に限らず、インドネシア国内に広く分布している。それどころか、シンガポールやマレーシア、オーストラリアにおいても、たやすくその店を発見することができる。このように広く点在するパダン料理店は、高級料理店としてではなく、庶民的で安価な料理として広まっている。パダン料理が広まっていった背景には、ミナンカバウ族の風習が深く関わっている。ミナンカバウ社会で、ミナンカバウ族の成人男性は、自分達の家族や親族のために成功をおさめたいという気持ちから、また、いわゆる出稼ぎのために、故郷である西スマトラ州をある一定の期間出て、主に商売で一旗揚げてくることを期待されている。 外に出て行った男達が各地でパダン料理レストランを開き、そのような男達によってパダン料理は広がっていった。パダン料理の最大の特徴はそのシステムにある。レストランや食堂のショーウィンドーには料理が洗面器のような器の中に入れられ、積み重ねてある。その積み重ねらせた料理の中から何種類か指定してご飯の上に盛ってもらう「アンペラ」という方式もあるが、こちらは安く食事をしたいときや、お金に余裕のない人達が多く利用する。しかし、本来のパダン料理式の食事では、レストランに入ってくると同時に、数人のウエイターが料理ののせられた直径15センチくらいの小皿を1人が5〜10皿ほどを腕にのせて運んでくる。席に座ると目の前にその運ばれてきた料理がひしめき合うように並べられる。その小皿の中身はというと、パダン料理の代表の「レンダン」という牛肉や水牛をココナッツと様々なスパイスで一晩以上煮詰めたもの、グライというカレーベースの鶏肉や魚、揚げた鶏や魚、焼き魚、山羊、イカ、コロッケのようなもの、スープ、それにちょっとした野菜等々があっという間に目の前に並べられる。そして、その中から、自分の食べたいものだけを選んで食べ、手をつけた皿の分だけ後で勘定をするというシステムになっている。自分の食べたものにだけお金を払えばいいので、何十種類と並べられた中で一皿しか手をつけなければ、当然、一皿分の値段だけを払えばいいことになる。また、パダン料理では、牛一頭、すべての部分を料理に使うという特徴がある。牛の脳みそから始まり、肺や胃、腸などの内蔵類、足、そして、皮も揚げてせんべいのように食べる。私も実際、牛の脳みそを食べてみたが、日本で狂牛病が騒がれるようになり、今更ながらぞっとする思いである。西スマトラ州の市場では、様々な野菜が売られているにも関わらず、こうしたパダン料理にはあまり野菜は使われていない。 まだきちんとした物資の流通システムが確立されておらず、また、すべての家に冷蔵庫があるわけではないこと、熱帯気候であることが関係し、十分に火を通したものでないと食べられないため、パダン料理は油を大量に使用する。また、このパダン料理を作るにあたって、大量の唐辛子も不可欠である。日本から見たイメージでは、インドネシア料理はとても辛いものとして捉えられがちだが、そもそもインドネシア料理というものは存在せず、実際、インドネシアの中でも、砂糖を大量に使用するジャワ料理と唐辛子をふんだんに使うパダン料理とでは全くものがちがう。パダン料理では、日本人の常識を超えた量の唐辛子を使用する。唐辛子にもいろいろな種類があり、赤いもの、緑色のもの、長さ15センチくらいのもの、そして、一番辛い緑色で長さ2センチくらいのものなどがある。ミナンカバウ族の食生活には必要不可欠な唐辛子であるが、ミナンカバウ族は乳幼児のころから唐辛子を食べ始めるため、日本人の成人がとても食べられない辛さのものを小さな子どもでも平気で食べている。ミナンカバウの人に言わせると唐辛子は体に非常にいいらしい。アペタイザーにもなるし、なにがどう関係するのかはわからないが、肌にもいいらしい。しかし、甘く見てはいけないのが唐辛子。中毒性があるらしい。そして長年食べつづけると舌の感覚が死んでしまうという。以上のことが関係してか、ミナンカバウ人は「辛くないものが食べられない」という奇妙な性質をもつ。ミナンカバウ人が知り合いのジャワ人の家で、食事をする機会があったが、ミナンカバウ人はかたくなに食事を遠慮する。もしかしたら拒否していると言ったほうがいいのかもしれない。ジャワでは料理は辛くない。ミナンカバウ人は辛くないものは食べられない。なぜかと聞くと、「味がしないから」だそうだ。 肉中心で野菜はあまり使われず、大量の唐辛子と油を使用するパダン料理。そのため、ミナンカバウ人にはハイコレステロール、心臓病が多い。たまに食べる分には美味しい料理だが、食べつづけると胸焼けのするのがこのパダン料理だ。 1年間ミナンカバウ人の社会で暮らす中で、パダン料理という食文化は、ミナンカバウ人のアイデンティティーと深く関わっているのではないかという印象を受けた。ミナンカバウ人は彼らの食文化を誇りに思う気持ちが強いのだと思う。だからこそ、外の世界へと出て行ったミナンカバウ人によって、パダン料理が広まったのだろう。 |
|
Copyright(C)2002 Ai Taniguchi. All Rights
Reserved.
|